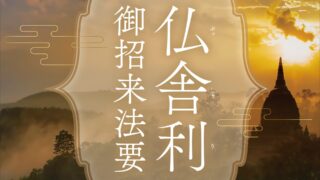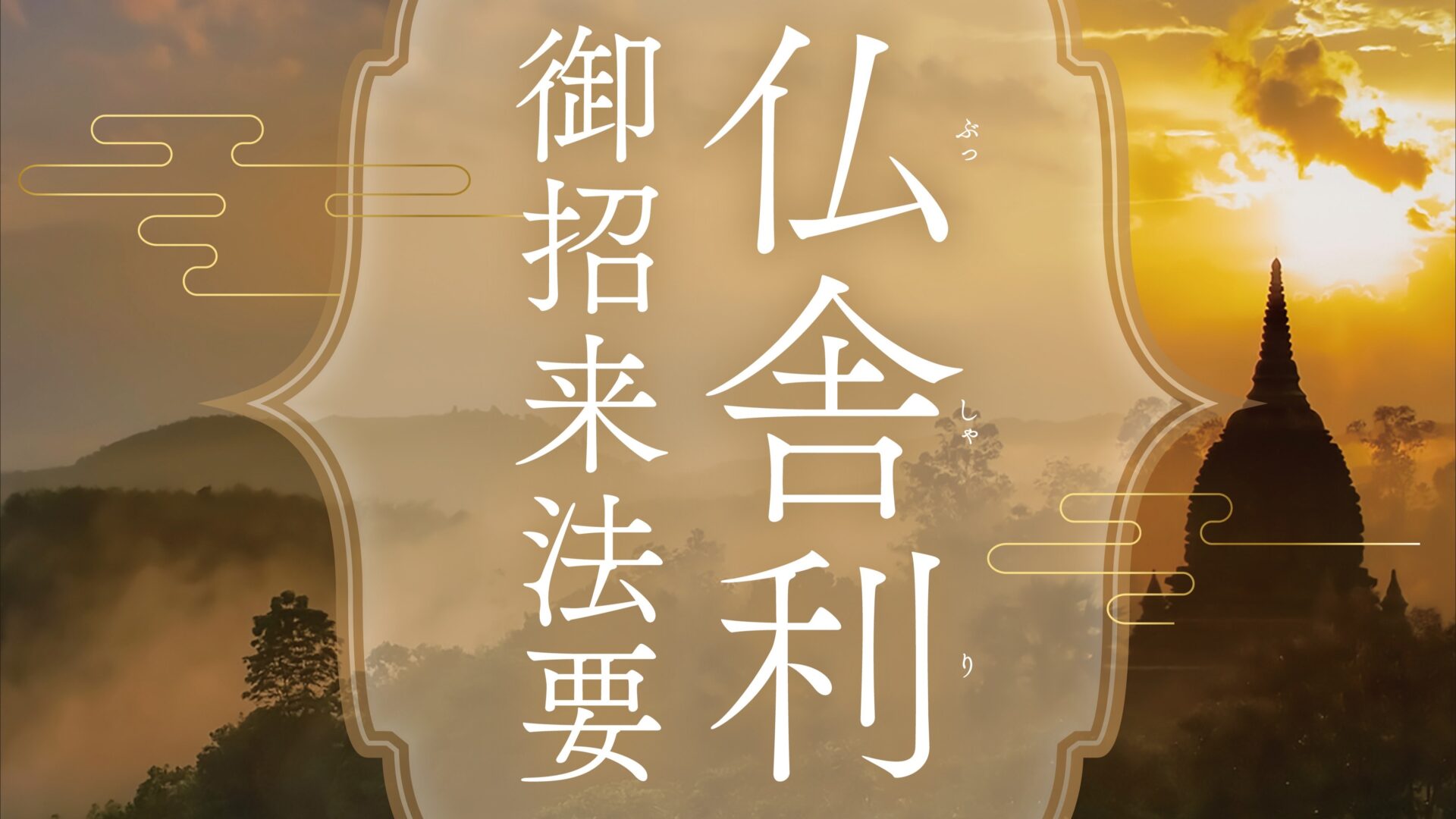日本における仏舎利信仰の変遷
仏舎利をまつるための建築物としての五重塔
日本において、仏舎利を祀る建築物として五重塔は重要な役割を果たしてきました。五重塔は、仏教建築の中でも象徴的な存在であり、その内部には仏舎利が納められることがあります。この形式は、インドの仏塔(ストゥーパ)の発展を受け継ぎ、日本独自の形に進化したものです。五重塔の各層は、下から地・水・火・風・空の五大要素を表しており、仏教の宇宙観(仏教の五大という概念)を象徴しています。仏舎利を安置することで、塔そのものが聖なる空間となり、多くの人々が祈りを捧げてきました。
古代日本における仏塔と仏舎利崇拝
古代日本では、仏教の伝来とともに仏塔が広まり、仏舎利崇拝も同時に根付いていきました。とくに、飛鳥時代や奈良時代に建立された仏塔は、仏舎利を安置する重要な役割を担っていました。たとえば、法隆寺や薬師寺の五重塔は、仏舎利が安置されたことで信仰の中心となりました。当時の人々は、仏舎利を直接拝むことで仏陀とつながりを持つと考え、その霊験を求めて巡礼や供養を行いました。仏舎利信仰を基盤として、古代日本の仏教は勢いを増し、多くの文化・建築物が発展するきっかけとなりました。
近世日本での仏舎利信仰の広がり
近世に入ると、仏舎利信仰はさらに広がりを見せました。この時期には、仏舎利が単なる遺骨崇拝の対象にとどまらず、象徴的な意味合いを持つようになります。とくに、江戸時代には仏舎利講という法会が盛んに行われ、多くの人々が仏舎利供養に参加しました。この時代の仏舎利崇拝は、仏舎利そのものだけでなく、その代用品である金属や木製の模造品を通じて行われる場合もありました。また、地域ごとに特色のある供養方法が生まれ、仏舎利信仰は日本各地に根付いたものとなりました。
日本の仏舎利観とその象徴性
日本では仏舎利が仏陀の遺骨を超えた象徴性をもつようになり、独自の解釈が発展しました。仏舎利は物理的な存在以上に、仏の教えや精神を受け継ぐものとして信仰されました。たとえば、遺骨そのものを見せるだけでなく、仏舎利の代用品やその象徴を通じて、仏陀の存在を身近に感じるという考え方が広まりました。また、日本独特の仏塔建築や五重塔がその象徴性をさらに強調し、多くの人々にとって仏舎利が仏教信仰の中核を成す存在となりました。このように、日本独自の仏舎利観は、物理的遺骨崇拝を超えた精神的価値をつくり出したのです。
摂津国分寺の仏舎利
もっとも、仏舎利観の元となる物理的遺骨崇拝が軽視されてきたわけではありません。これまでも、物理的に存在することは重視されてきたのですが、仏舎利の度重なる分骨によってその崇拝が薄らいでいただけでした。その意味で、この度、ネパールより摂津国分寺へ御招来される仏舎利は大切なものであり、また、寺院として精一杯に御招来を受け止めたいと考えています。