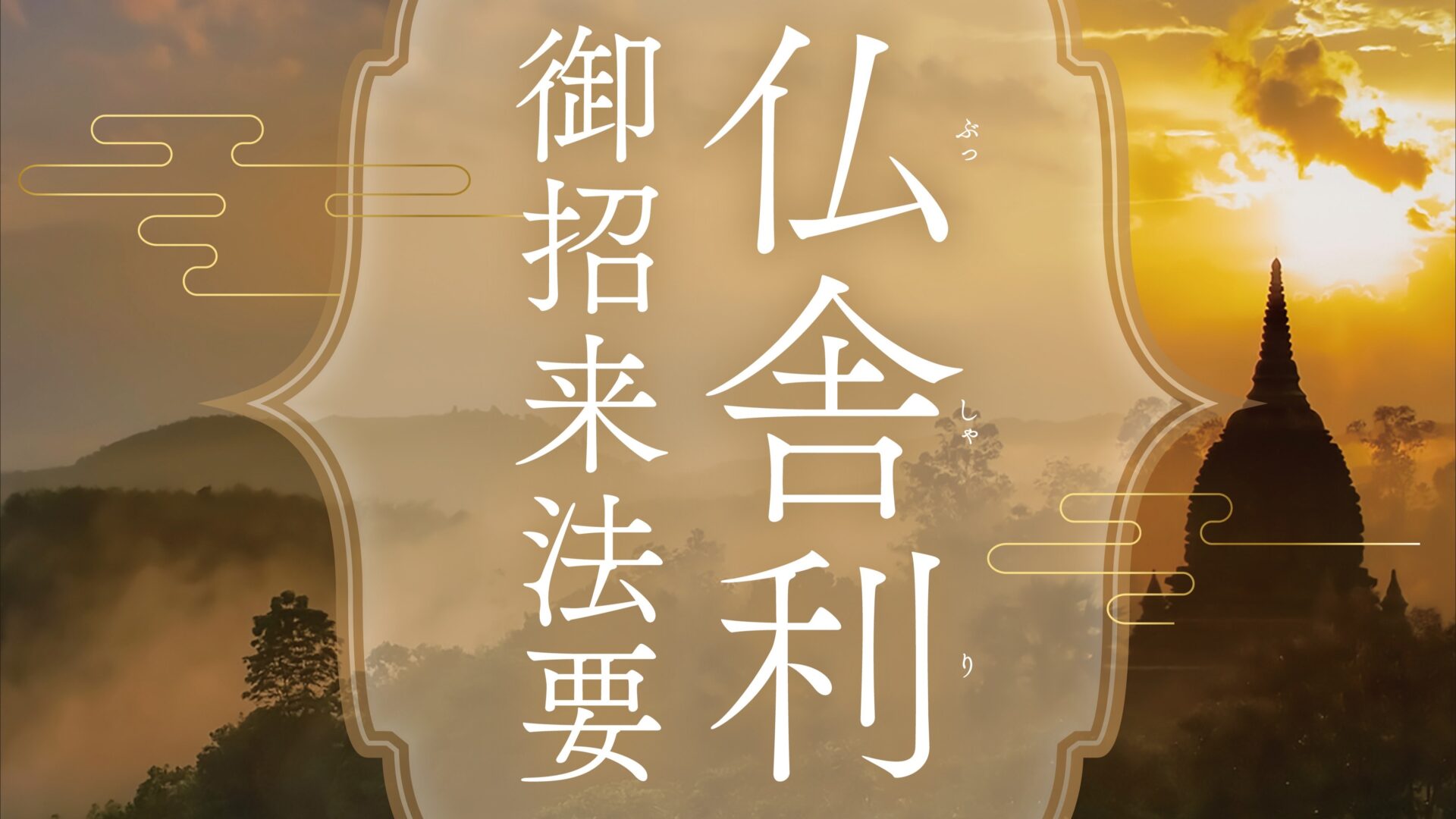仏舎利御招来法要
摂津国分寺では、きたる5月18日(日曜日)、13時より昭和金堂にて仏舎利御招来法要を行ないます。
みなさんは、舎利(シャリ)と聞いて何を連想されますか?
シャリは仏教用語にもお寿司屋さん用語にも使う言葉。共通する意味合いを漢字一つでいえば「粒」といったところです。仏舎利は仏様の舎利。以下では、この言葉を丁寧にみていきましょう。
仏舎利とは?
仏舎利の定義と由来
仏舎利とは、仏教において釈迦などの高僧の遺骨や遺灰を指します。その語源はサンスクリット語の「シャリーラ」に由来し、身体や遺骨という意味をもちます。仏舎利は、ふつう火葬後に残る骨や灰を意味しますが、聖なる存在の象徴でもあり、仏陀の霊的な力が宿ると信じられています。この信仰は仏教が誕生する以前のインドにおける遺骨崇拝の文化的背景にも根付いています。
仏舎利のサンスクリット語「シャリーラ」の意味
サンスクリット語の「シャリーラ」は、身体や構成要素を意味します。この言葉には肉体という物理的な存在だけでなく、精神的な象徴としての意味も含まれています。釈迦の火葬後に遺骨が八つの部族に分配された「舎利八分」の伝承は、仏舎利が単なる身体の遺物ではなく、釈迦の教えや精神の象徴としても重視されていることを物語っています。
遺骨崇拝の背景と宗教的意義
遺骨崇拝は古代インドに根付く文化的な慣習に由来します。インドでは遺骨が人々を守り、霊的な加護を与えると信じられてきました。この文化が仏教に取り入れられ、仏舎利の信仰として発展していきます。特に仏舎利は、釈迦の教えが絶えることなく後世へと受け継がれる象徴として重要視されてきました。そのため、仏舎利を供養する仏塔や儀式が広く行われ、やがて大衆信仰とも深く結びついていきました。
仏舎利と仏塔(ストゥーパ)の関係

Image by Joakim Mosebach from Pixabay
仏舎利と仏塔(サンスクリット語ではストゥーパ)は密接に関係しています。仏塔はもともと釈迦の遺骨を安置するために建てられた墓標でしたが、次第に仏教信仰の象徴として意味が拡大しました。ストゥーパは釈迦の精神と存在の象徴とされ、多くの場合、巡礼や供養の拠点となっています。また、仏教が広がるにつれて仏塔の構造や意味合いは地域ごとに変化し、五重塔などの形で日本にも受け継がれています。